僕のジョバンニは穂積さん作、現在連載中のチェロ弾きの少年二人の物語です。天賦の才能と努力の天才の二つの才能のぶつかり合いがストーリーの軸になっています。現在4巻まで発売中。未完結作品なので、1巻づつ紹介していきます。
手塚鉄雄は小学生。海沿いの小さな町でただ一人チェロを弾く子供です。以前一緒にチェロを弾いていた兄の哲郎はすでにチェロを辞めており、学校の友達もチェロに対する鉄雄の思いなど到底理解できるはずもなく、孤独な日々を送っています。鉄雄のチェロの腕前は小学生ながら大きな大会で優勝するほどですが、鉄雄は一人ではなく誰かと弾きたいのです。哲郎にもう一度弾いてほしい、一緒にやってほしいと頼みますが、鉄雄を可愛がっている哲郎は
「それだけはできない。」
と断るのでした。
橘・A・郁未(たちばな・アレックス・いくみ)は海難事故のただ一人の生存者として鉄雄の住む町に流れ着きます。郁未は海に投げ出されたとき自分を呼ぶ声を聞き、その声の元に必死に泳ぎ着きます。実はその声は鉄雄の弾くチェロの音色だったのです。郁未はその事故で母親を亡くし、外国人の父親も親戚もまったく頼るもののいない孤児となってしまいました。身元引受人がいないため、鉄雄の家に預けられることになります。
初めて会った郁未は口をきかず、鉄雄は郁未に
「お前、愛想ねえな。」
と言い放ちます。
ある日、鉄雄は弾くチェロを耳にした郁未は、海で自分を呼ぶ叫び声が鉄雄のチェロだったと悟ります。
それから郁未は、鉄雄のそばを離れず毎日チェロを聴くのでした。
郁未は哲郎から、鉄雄がいつも弾いている曲「チェロよ、叫べ」が本来は2挺で弾く曲だと聞き、自分が弾くから教えろと鉄雄に頼み、鉄雄は喜んで郁未に基礎からチェロを仕込みます。郁未は鉄雄の、誰にも理解されないという孤独を知り、それを「天才の孤独」と呼びます。郁未は自分だけは一生友達でいると誓うのでした。
「鉄雄は太陽の匂いがする。だから、お前を絶対に裏切らない。」
鉄雄と郁未の友情が深まっていったある日、手塚兄弟の祖父の古い知り合いでプロのチェリストの曽我百合子が手塚家にやってきます。
いつの頃からか百合子を苦手とするようになった鉄雄は浮かない顔です。それを知った郁未は自分も百合子とは口をきかないと言います。鉄雄は百合子から数年前に言われたある言葉に呪縛され苦しんでいました。
郁未は手塚家に正式に引き取られます。姓が変わっていないので、おそらく里子なのでしょう。郁未は鉄雄にだけ心を開き、少しでも離れることを嫌がります。その郁未を見て、手塚家の両親が郁未を引き取ることを決めたのです。今、鉄雄を引き離すことはできないと考えたのでした。郁未の鉄雄に対する感情は、友情というには激しすぎるものでした。
百合子は毎年夏に一か月ほど手塚家に滞在します。鉄雄が栃木の母方の祖父の家に遊びに行っていた一週間で、郁未は百合子の弾く曲を聴いて覚え、真似して弾けるようになります。その演奏を鉄雄に聴かせ、
「簡単だった。だから百合子なんて大したことない。あいつの言葉なんかで苦しむな。」
郁未は鉄雄を励まし、喜ばせるつもりで言ったのです。が、それは百合子に言われた言葉よりも何倍も深く鉄雄を傷つけます。
郁未が一週間で耳コピしたその曲は、チェロの曲の中でも最も難曲とされる曲でした。そして、鉄雄はまだその曲を弾けないのです。
本当の天才は郁未だったのです。これで鉄雄を百合子のかけた呪いから救うことができたと信じ、満面に幸せそうな笑みを浮かべる郁未と、この世の終わりのような絶望的な表情の鉄雄のアップが読む方も辛くなります。まだ小学生の二人が、これから才能というものに苦しむことを予感させます。一人は才能がない故に、もう一人は才能がある故に。
郁未がチェロをはじめたのは鉄雄を一人にしないためで、鉄雄が2挺のチェロで合わせたがっていた「チェロよ、叫べ!」を二人で弾くためです。この「チェロよ、叫べ」は架空の曲ですが、モデルとなっているのは「チェロよ、歌え」という曲です。歌うを通り越して叫んでしまうんです。その叫びは鉄雄の孤独の叫びであり、その声を聞いた郁未を引きつけ、命を救った叫びなのでしょう。これから成長していく二人がどうなるか、楽しみに追っていきます。
「チェロよ、叫べ!」のモデルとなった「チェロよ、歌え」はこちら。

【輸入盤】ホーナー:パ・ド・ドゥ、ペルト:フラトレス、ソッリマ:チェロよ歌え!、エイナウディ:希望の扉 サムエルセン兄妹、ペトレンコ&リヴ [ James Horner ]
【輸入楽譜】ソッリマ, Giovanni: チェロよ歌え!(8本のチェロ): パート譜セット [ ソッリマ, Giovanni ]
郁未が一週間で耳コピした難曲、チェロ協奏曲はこちら

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 他、エルガー:チェロ協奏曲 他 [ ジャクリーヌ・デュ・プレ ]

日本語ライセンス版 ドヴォルジャーク : チェロ協奏曲ロ短調op.104 小型スコア スプラフォン社日本語ライセンス版
2巻はこちら
3巻はこちら
4巻はこちら
5巻はこちら


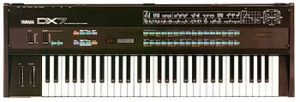









最近のコメント